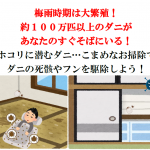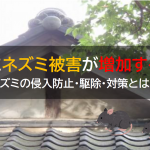- 0800-919-6866年中無休 9:00-18:00
- 無料見積もりはこちら
3分でわかる!ネズミ対策のポイント
「ん?これはネズミ被害かもしれない」といった以下のような兆候を感じたことはありませんか。
屋根裏や壁から音がする
食べ物が食われている
小さなフンを見つけた
かじり跡や足跡などの痕跡がある
獣臭やアンモニア臭がする
床や壁、配線の損傷などの物理的な異変がある
上記のような被害を感じたら、ネズミ自体を見ていなくても家のどこかにネズミが侵入している可能性があります。
警戒心が強く、賢いネズミは、深夜、人間が寝静まった頃に活動します。
ネズミが建物に住み着くと、健康面や建物へ、様々な悪影響をもたらすおそれがあるため、駆除や予防対策が重要になります。
こちらのコラムでは、3分でわかる!
ネズミ駆除対策に関するポイントをご紹介します。
目次
建物に侵入する3種類のイエネズミ

クマネズミ
体長 15㎝~20㎝
子供の大きさは5~10㎝程度。
生後2.5~3.5ヵ月で大人と同様の大きさになる。
イエネズミの中でクマネズミによる被害が最も多い。警戒心が強いため、駆除が難しい。
主に屋根裏などの乾燥した高い場所を好み、木登りや綱渡りが得意。
殻物や植物質を好んで食べる傾向がある。
ハツカネズミ
体長 7㎝
すばしっこく好奇心旺盛。
イエネズミの中で最も小さく、わずかな隙間から侵入する。
子ネズミと間違われやすく、繁殖力が強い。
殻物や植物質の物を食べる。
屋内や倉庫などにも住み着く。
ドブネズミ
体長 20㎝
イエネズミの中で最も大きい。
凶暴で警戒心はない。
床下や土中、下水管など、ジメジメ湿った場所に住み着き、後足が発達して泳ぎも得意。
高い場所には登れない。
雑食性で生ゴミなど何でも食べる。
ネズミによる被害とは
かじられる被害
キッチンやお部屋に保管している食品以外にも、石鹸や壁、天井板、柱、配線や電線などをかじり、故障や漏電火災につながる場合がある。食べる行為だけでなく、自身の伸び続ける歯を削るためにかじることもある。
足音などの騒音被害
夜間、人が寝静まっている時間帯に屋根裏や壁の内側を走り回ったり、何かをかじる不快な音がする。
個体数が増えれば、騒音被害が原因で住人にとって不眠などの精神的ストレスを与えることがある。

糞尿被害
餌場やねぐらの周辺に多くのフンをしたり、移動しながらフンを落としていく。
ネズミの糞尿には、サルモネラ症、レプトスピラ症、ハンタウイルス感染症など、病原体や寄生虫を含み、健康被害を起こす可能性がある。
フンに含まれる病原体を吸い込んだり、フンが付着したものを直接触ったりすることで感染することもある。
排泄物によって悪臭や害虫の発生。健康被害ではネズミの体に付着した細菌やウイルスで食中毒の原因になる場合もある。
天井板などの汚染、腐食なども起こる。
ダニの発生
ネズミは不潔な環境にいることが多く、ダニやノミが寄生していることが多い。
雑菌の運び屋とも言われているゴキブリの数百倍以上の菌類をネズミの体にも寄生しているため、移動するたびにダニや細菌、ウイルスを運んでいることになる。
ネズミの体に寄生するダニは、イエダニという吸血性のダニ。ネズミが移動あるいは死亡していなくなると、イエダニは室内を移動して新たな吸血源となる人を吸血するため、ダニによる二次被害が起こる。
ネズミ予防対策
エサを与えない環境づくり
ネズミ予防に重要なのは、エサを与えない環境を維持すること。特に夜間、人間がいない又は寝静まっている時間帯に活動するため、キッチンやお部屋、屋内外の食品やゴミ箱を片付け、蓋付きタイプのゴミ箱を使用したり、常温で保管している米や乾麺など、食害されるおそれがあるものは、かじられないよう保管方法に注意し、エサを与えない環境をつくる。
住処・隠れ家を作らない
ネズミは掃除の行き届かない屋根裏や壁と壁の隙間の断熱材などを住処にする。侵入口を塞いで侵入を防止することが重要になるが、ダンボール類などもかみ砕いて寝床を作るため、屋内外の荷物の整理や不要になった荷物やゴミ類を処分しておくことで巣材被害が防げる。
侵入口を塞ぐ
最も重要になるのが、ネズミの侵入口を塞ぐこと。ネズミが出入りしているわずかな隙間やかじり跡、足跡の汚れが付いた壁の隙間はネズミのラットサイン。金網ネットやトタン板などで塞ぐことで侵入を防止できる。
床下通気口、通風孔など、劣化で隙間がある場合、通気を損なわないために金網で塞ぐのが有効的。ガムテープなどで塞いでもネズミがかじって剝がされる可能性があるのでしっかり塞ぐことが重要。
ネズミの駆除方法
追い出しや粘着シートで捕獲する
市販でも販売されているネズミ用の忌避剤による追い出しや粘着シートをネズミの侵入経路(ネズミが出入りしている)付近に設置し、しばらく経過観察をする。忌避剤は一時的な効果が期待できるが、侵入口があれば再び侵入される可能性がある。
トラップにかからない場合、フンが落ちていたり、ネズミが出没しているエリアに敷き詰める。
ネズミは警戒心が強いため、「いつもと違う」と感じたら、近寄らなくなることもあるので、粘着シートに米などのエサを一緒に設置しておくと効果的。ネズミがかかったら粘着シートごとゴミ袋に入れて密封し、速やかに処分する。
毒エサを設置する場合の注意点
毒エサを設置する場合、人が誤って口にしないよう設置場所に注意が必要。
ネズミの毒エサの効果は、配合されている殺鼠剤の種類によって異なります。
即効性のある毒エサや遅効性のある毒エサなどがあり、ネズミに警戒心を与えずに食べさせ、確実に駆除するために、効果が出るまで時間差を持たせた遅効性の毒エサが一般的。遅効性の毒エサは3~5日間程度食べ続け、体内で毒成分が蓄積され、死に至らしめるもので、食べてすぐに効果が出るものではありません。
速効性の毒エサは、少量でも口にすれば短時間で効果が表れ、短時間で駆除が可能。しかし、ネズミが毒エサを食べた後に苦しむ姿を見て、他のネズミが警戒して毒エサを食べなくなる可能性がある。
どちらのタイプであっても屋根裏、床下など、人やペットが誤飲・誤食しないような場所に設置し、保管や設置場所に厳重に注意する。
毒エサを設置するだけでなく、侵入経路を塞がない限り新たなネズミが侵入する可能性があるため、侵入経路の特定と隙間の封鎖が重要。
自分で対策が困難な時は業者に依頼
警戒心が強く、賢いネズミを駆除するのは至難の業と言える。自分でネズミ対策をしても
「罠にかからない」
「どこに設置したら良いのかわからない」
「繰り返し被害が続いて困っている」
「死骸処理に抵抗がある」といった声も多い。
駆除業者に依頼すると、効果的な施工で徹底的に駆除し、死骸回収も行ってくれるため、自分で対策が困難な場合は業者に依頼する方が効率的と言える。建物の構造や被害状況によって施工内容・駆除費用も異なるため、まずは現調見積もりを依頼することをおすすめします。